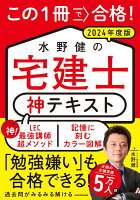【2024年6月26日】
更新情報:水野講師が『水野健の宅建士 神問題集』の動画解説を続々アップ。『神テキスト・神問題集』セクションをご参照ください。
宅建は20万人以上が受験する超大型資格試験。
受験規模が大きいため市販宅建テキスト・問題集・漫画は数十冊も発売されています。書店やネットで選ぼうとしてもどれが良いのか途方に暮れる受験生は少なくないでしょう。
そんな宅建受験生のために、当サイトでは宅建市販テキスト・参考書・問題集・漫画11シリーズ50冊以上を実際に全て購入。宅建独学・初学者におすすめできるテキスト・問題集・漫画を吟味してきました。
この記事では「宅建合格のための3段階学習法」を提案し、50冊以上の宅建テキスト・問題集の中から3段階学習法に適した「合格に直結する宅建テキスト・問題集」を紹介します。
まずは3段階学習法をお読みいただき、それからおすすめテキスト・問題集のレビューに目を通してご検討ください。
令和6年度(2024)宅建試験合格目指してがんばりましょう!

- 宅建合格のための3段階学習法について
- 第2段階学習におすすめ:宅建士 合格のトリセツ基本テキスト
- 第3段階学習におすすめ:出る順宅建士 ウォーク問過去問題集
- 第2段階・第3段階学習用テキストと問題集を2冊に集約したい場合におすすめ:『宅建士 神テキスト』・『宅建士 神問題集』
- 5問免除対象の受験生および条文番号も含めて学習したい受験生向け:『出る順宅建士 合格テキスト』
- 『とらの巻』、『直前予想模試』について
宅建合格のための3段階学習法について
◆宅建試験は50問出題されます(5問免除者は45問)。
宅建試験の合格するためには、受験年度の宅建試験合格基準点以上を得点しなければなりません(5問免除者は5点マイナスしてください)。
平成28年度以降の宅建試験合格基準点は50問中35〜38点。
したがって、最低でも35点、できれば38点以上は取りたいところです。
では宅建合格基準点を取るにはどうすれば良いでしょうか?
その答えはシンプルです。
合格者正解率66%以上の問題を確実に得点することです(詳細は当サイトの『【宅建合格のために】合格者正解率(正答率)50%以上の過去問を確実に解こう!』を参照)。
合格者正解率66%というのは「宅建合格者の3人に2人以上が正解する」問題、すなわち基本的な問題に他なりません。
宅建合格に必要なのは基本的な問題を取りこぼさないことに尽きるのです(正解率が低い難問・奇問を得点する必要はありません!!)。
◆ちなみに平成30年度試験は合格者正解率75.9%以上の問題、つまり合格者4人のうち3人が正解できた問題さえ取りこぼさなければ合格基準点37点で合格できました。
宅建で合否を分けるのは正解率が低い難問・奇問ではありません。
宅建で合否を分けるのは正解率が高い基本的な問題なのです。
基本的な問題を取りこぼさないことが宅建合格への最短コースなのです。
◆では宅建試験で基本的な問題を取りこぼさないための学習とは具体的に何をすれば良いのでしょうか?
すべきことは次の3つです。
- 宅建試験の範囲を把握する
- 基礎をしっかり固める
- より多くの過去問を習熟しつつ法改正点をおさえる
この考えに沿った3段階学習法およびそれぞれの段階に適したオーディオブック・テキスト・問題集を紹介します。
第1段階:『パーフェクト宅建士聞くだけ』を使って宅建試験全範囲を1週間〜10日間で把握する
◆宅建本試験で出題されるのは50問。
内訳は「民法等」14問、「宅建業法」20問、「法令上の制限」8問、「その他関連知識」8問です。
出題される法律は・・・民法、借地借家法、区分所有法、不動産登記法、宅建業法、都市計画法、建築基準法、国土利用計画法、農地法、宅地造成等規制法、土地区画整理法、所得税、印紙税、不動案取得税、固定資産税、不動産鑑定評価基準、不当景表法、住宅金融支援機構法などなど。
まずはこれら「宅建試験出題範囲を把握すること」から宅建学習を始めましょう。
◆第1段階に最適な教材は『パーフェクト宅建士聞くだけ』です。
最適である理由は次の3つ。
- 無料で利用できる(これが何より)
- わずか12時間29分(1.2倍速なら10時間24分)で宅建試験全範囲を把握できる
- 耳から聞くことで知らない法律用語になじみやすくなる
何のとっかかりもないままテキストをいきなり読み始めると・・・見たことも聞いたこともない法律用語の連発に心が折れかねません。
せっかく買ったテキストを第1章を開いただけで二度とテキストを開かないことだってありえます。
これは宅建漫画でも同じです。宅建漫画は入門用教材として決して悪くはありません。ただ、中には漫画は各項目の導入に1ページだけ描かれていて残りはテキストを薄めた内容のものも混ざっています。
管理人は宅建漫画6冊についてレビューしていますが、おすすめできるのは全編漫画形式で編集されている1冊だけ。ただし¥2,420かかります。
お金を出して宅建漫画・宅建テキストを買う前に、まずは無料教材から学習することを強くおすすめします。
◆『パーフェクト宅建士聞くだけ』は1.2倍速でも違和感なく聞けます。1.2倍速で朝・昼・晩に30分ずつ聞くと7日間で聞き終えられます。
まずは『パーフェクト宅建士聞くだけ』を聞き、宅建試験の範囲を把握することから宅建学習を始めましょう。
※もし全範囲を聞くのが難しいようでしたら権利関係だけでも聞いてみてください。それなら4時間32分で済みます。
第2段階:周回しやすいメインテキストと一問一答問題集を使って基礎を固める
◆第1段階の『パーフェクト宅建士聞くだけ』を1週間〜10日ほどで終えたら第2段階の「基礎固め」に移行します。
基礎固めの第1歩は「30日間でテキストと問題集を完走すること」です。
おすすめするのは600ページ程度のメインテキスト。1日20ページ学習すれば1ヶ月で終えられます。
◆宅建テキストは何十冊も出版されていますが、ページ数で分けると3グループに集約できます。
・600ページ前後
・700〜800ページ
・1200ページほど
これらのうち基礎固めに向いているのは「600ページ前後」のテキストです。ページ数の少ないテキストのほうが反復学習しやすいからです。
※600ページ前後のテキストだからといってなんでも良いわけではありません。中には2023年度宅建試験問2で出題された相隣関係をまったく掲載していないものがあります。そのテキストは600ページ未満ではありますが、合格に必要な項目を収録していないので論外です。もちろん当サイトでは一切おすすめしていません。
初学者におすすめするのは、
- 各単元の冒頭に学習ポイントが明記されているもの
- 条文番号がないもの(宅建業法34条、35条、37条および農地法3条、4条、5条を除く)
- 出題可能性が低い項目をカットしているもの
1. 宅建テキストの各単元には頻出項目とそうじゃない項目が混在しています。各単元で重点的に学習することを明確に示すのが学習ポイント(「コースの特徴」や「攻略メモ」等も含む)です。
これがないと、テキストに書いてあること全てを等しく学習させられかねません。例えば何の注釈もなしに宅建業法の罰則がずらずら並んでいたら全部覚えなきゃならないと思ってしまいます(宅建業法の罰則を全て覚えておく必要がないとわかったのは宅建受験2年目のことでした。無駄なことをしてしまいました・・・)。
宅建では頻出項目を重点的に学習するのが王道です。頻出項目の問題は受験生がきっちり学習しているため、合格者正解率が高いからです。
その単元で何を重点的に学習し、何が深入り厳禁なのかを明記していないテキストはおすすめできません。
2. 条文番号は宅建合格には不要です。ただし、宅建業法34条、35条、37条および農地法3条、4条、5条は頻出項目ですので、かならず覚えておきましょう。
3. 宅建試験では、例えば国土利用計画法の監視区域・注視区域・規制区域は過去10年の宅建試験でほとんど出題されていません。にもかかわらずこれらについても丁寧に丁寧にページを割いて解説しているようなテキストがあります。そんなテキストはおすすめできません。
※宅建初学者の中にはより詳しいテキストを欲しがる方がいます。人それぞれなので止めはしませんが、ページ数が多いほど完走しにくくなります。宅建試験合格にはテキストを最低でも6周しないと知識が定着しません。周回しやすい=反復学習しやすいテキストを選ぶことを強くおすすめします。
周回しやすいテキストと一問一答問題集を1ヶ月以内に完走したら、次は一問一答問題集を反復して正解率を100%にもっていきます。
わからなかった問題は必ずテキストを参照しましょう。中にはテキストに書かれていないことも出題されます。その問題については解説をしっかり読み、解説から必要事項をテキストに書き込んでおくと良いでしょう。
問題を解くときは単に○×を当てるだけではダメです。その問題がなぜ○なのか?なぜ×なのか、その根拠を明確に理由付けできるまで繰り返すことが大切です。
なんとなく○、なんとなく×、答えを見たら○だった×だった、などというレベルで問題を解いてもなんにもなりません。
できれば「正解の問題はここをこう変えれば不正解になる」、「不正解の問題はここをこう変えれば正解になる」というレベルまで知識を高めると第3段階がとても楽になります。
なお、一問一答問題集は図表付きで解説されているものが良いです。試験範囲のうち、とりわけ権利関係は「図を書く癖を付ける」と解きやすくなるからです。
できれば2024年6月いっぱいまでに第2段階学習を終えましょう。
第3段階:より多くの過去問を習熟しつつ法改正点をおさえる
◆第2段階(基礎固め)でようやく宅建試験を受験するベースが出来上がりました。
次の第3段階の学習では「本試験と同じ4肢択一形式問題を習熟しつつ法改正点をおさえる」ことで、本試験受験に向けたの準備を整えます。
◆宅建試験の市販4肢択一形式問題集は300問程度のものが多いです。ただ、これでは習熟用としては収録問題数が足りません。
市販宅建テキストで収録問題数を満たしているのは550問を収録している『出る順宅建士 ウォーク問過去問』と667問・677問を収録しているその他2つの3シリーズです。
これらのうち、第3段階に向いているのは550問問題集です。というより、『ウォーク問』が最適です。
最適である理由は次の2つ。
- 600問以上を収録した問題集よりも完走・周回しやすい
- 習熟用宅建問題集のうち、唯一合格者正解率データを記載している
667問・677問問題集より、550問を収録している『ウォーク問』のほうが問題集の完走および周回に向いてます。
そして、こちらのほうがむしろ重要なのですが、『ウォーク問』には合格者正解率・合格者不合格率・受験者正解率の3つのデータが問題それぞれに記載されています。
とりわけ、合格者正解率は宅建合格にとって非常に重要です。な合格者正解率66%以上の問題は確実に取らなければ宅建合格は困難です。
『ウォーク問 過去問題集』は最低でも1日19問解くことを目標にしましょう。1日19問解ければ1ヶ月で550問を1周できます。
できれば2024年7月いっぱいまでに550問を完走し、残りの期間で何度も周回して特A・A・B問題の正解率を100%に仕上げましょう。
◆法改正点は『どこでも宅建士 とらの巻』、法改正情報を掲載している直前予想模試、さらには『トリセツ』の法改正情報のいずれか、もしくは全部を使っておさえましょう。
『どこでも宅建士 とらの巻』は例年5月下旬発売と市販テキストでは発売日がもっとも遅いですが、その分、法改正点が網羅されています。例年、テキストには最新改正点のみならず過年度改正点にもマークが施されています。
また、別冊付録の直前暗記集『どこでも宅建士 とらの子』がものすごく便利です。『とらの子』は宅建基本知識を切り離せる小冊子です。どこでも持ち歩き、ボロボロになるまで使い倒しましょう。
◆直前予想模試のおすすめは日建学院もしくはTACの直前予想模試です。前者は新旧対照表を用いているので法改正点がわかりやすいです。後者は法改正点を最も多く記載しています。
LECの直前予想模試(『出る順宅建士 当たる!直前予想模試』)の2023年版には法改正情報が掲載されていませんでした。2024年版もそうなる可能性があります。
◆おおまかな学習スケジュールです。
- 第1段階(試験範囲把握):学習開始1週間〜10日
- 第2段階(基礎固め):第1段階終了後2〜3ヶ月
- 第3段階(過去問習熟と法改正情報入手):第2段階終了後から宅建本試験まで
2024年3月中旬からだと、
- 第1段階:3月下旬まで
- 第2段階:4月から6月末
- 第3段階:7月から10月20日宅建本試験まで
注:2024年9月後半になったら最新統計情報も必ず入手してください。
第1段階学習におすすめのオーディオブックは『パーフェクト宅建士聞くだけ』です。
では第2段階・第3段階学習でおすすめする宅建テキスト・問題集を紹介します。
※3段階学習の欠点は、第2段階で宅建テキストと一問一答問題集が、第3段階で『ウォーク問過去問題集』3冊の合計5冊が必須なことです。
この欠点を補い、宅建テキスト・問題集の2冊で学習の質・量を確保できるのが、今年新たに発売された『神テキスト』・『神問題集』です。
第2段階用として当サイトでおすすめしているのは『トリセツ』ですが、『トリセツ』の紹介の後に『神テキスト』・『神問題集』についても紹介しておきます。
第2段階学習におすすめ:宅建士 合格のトリセツ基本テキスト

- 条文番号:無
- テキスト部分のページ数:550頁
- 色使い:フルカラー
- 読みやすさ:読みやすい
- 分冊の有無:有 4分冊
- 電子書籍の有無:有 Kindle版と楽天Kobo版
- 問題集との連携:『頻出一問一答式過去問題集』と双方向連携
- 内容について(国土法):○
第2段階学習に最もおすすめしているのはLEC『2024年版 宅建士 合格のトリセツ 基本テキスト』です。
『トリセツ』をおすすめする理由は次の3つです。
- 内容を適切に絞り込んだ上で「索引付きで600ページ以内」に編集。完走しやすい。反復学習に適している。
- 読みやすくデザインされている。
- 一問一答問題集と連携している。しかも一問一答問題集は収録問題の約9割がAランク問題なので初学者にうってつけ。
『2024年版 宅建士 合格のトリセツ基本テキスト』はフルカラーの分冊タイプです。テキスト部分は3分冊合計550ページ。
第2段階学習向け600ページ未満のテキストです。
宅建は基礎知識の徹底が何より大切な資格試験。1,200ページのテキストを5周するより600ページのテキストを10周するほうが効果的です。
昨年版よりも9ページ増えましたが、それでも市販宅建テキストの中ではトップクラスのコンパクトさです。繰り返し学習に最適な一冊です。
2024年版には巻末付録として「重要論点集」47ページ分を収録。こちらも分冊できます。
手に取るとけっこう分厚いです。分冊したときにペラペラにならないよう各分冊を厚紙で挟んでいるからです。
付録に分冊背表紙シールがありますので、購入したらすぐに分冊しておきましょう。
インデックスシールも付いてるので、各項目にシールを貼ると目当ての項目をすぐ開けられます。
※以前は付箋も付録についてましたが2023年版から付箋とスマホ対応一問一答PDFデータがアンケート特典になりました。
購入者限定特典として無料講義動画45回分を視聴できます。他のテキストにはない本書の大きなメリットです。
分冊時にボリュームがわかりやすいよう、各分冊は1ページ目から始まります。権利関係〜税・その他までページ番号を通しているテキストもありますが、ページ番号を各分冊ごとに分けた方が分量を把握しやすいです。
国土法にいたっては「許可制については出題されることはほぼないと思いますので省略しました(法令上の制限p.79)」とあります。
出題可能性が低い事項まで勉強する必要は一切ありません。
『トリセツ』は「縦線と横線の太さに差がない読みやすい」ユニバーサルデザインフォント系のフォントを採用。フォントも宅建テキストとしては大きめで読みやすいです。
余白もしっかりとってあるので、書き込みながらの学習にも適しています。
2024年版トリセツテキストにはとても大きな改善点がありました!
それは各コースの最初のページに『宅建士合格のトリセツ 頻出一問一答式過去問題集』の該当番号を表示したことです!
昨年までも『トリセツ』テキストと問題集はリンクしていたのですが、分野別問題集(および一問一答問題集)にテキストの該当コースが記載されているだけ。つまり問題集→テキストという方向でしかリンクされていなかったのです。
今年度版はテキスト→問題集という方向にもリンクが施されました。管理人が知る限り、宅建テキストで初めてテキストと分野別問題集・一問一答問題集のリンクが双方向になったのです。
テキスト→問題集という方向のリンクは、TACの『みんなが欲しかった!宅建士の教科書』とユーキャンの『宅建士 基本の教科書』には採用されていたものの、2024年版では分野別問題集のみで一問一答問題集へのリンクはありません。
テキストと分野別問題集・一問一答問題集のリンクが双方向になったことでより受験生に便利となり、数ある宅建テキストの中でも『トリセツ』が一歩優位に立ちました。
◆本書の欠点はどこが法改正点かわからないことです。「本書ご購入者のための特典」の「2024年法改正情報」(冒頭「用語集」の次のページ)をダウンロートして必ず補ってください。
※『宅建士 合格のトリセツ 基本テキスト』は全44コース。
1日で2コースずつこなせば22日間で1周完走できます。
22日間じゃなくてもかまいませんので、「テキスト1日20ページ・一問一答問題集30問(30肢)」を目安に毎日取り組み、30日間で絶対完走しましょう。
LEC宅建士合格のトリセツシリーズには、分野別4肢択一の『宅建士合格のトリセツ 厳選分野別過去問題集』、一問一答問題集の『宅建士合格のトリセツ 頻出一問一答式過去問題集』があります。年度別問題集はありません。
◆一問一答問題集の『宅建士合格のトリセツ 頻出一問一答式過去問題集』は2024年版の紹介です。

- サイズ:テキストと同じA5判
- ページ数:権利関係145頁、宅建業法112頁、法令上の制限85頁、税・その他55頁
- 分野毎の収録問題数:権利関係266問、宅建業法232問、法令上の制限181問、税・その他121問
- テキストとの連携の有無:有 『宅建士 合格のトリセツ 基本テキスト』とリンク
収録問題数は800問(800肢)。
問題(肢)に年・問題番号・肢番号が付されています。過去問ベースの一問一答問題集です。
問題は見開きの左ページに、解答・解説は右ページにあります。付録の「解答かくしシート」を右ページにかぶせながら問題を解くとよいでしょう。
解答・解説には「一言解説」が付されています。「一言解説」は「問題を解く上でのポイント」です。問題を解いたら必ず目を通しておきましょう。
問題は出題頻度によって★★★〜★マークあり。
- ★★★→「出題頻度が高い問題」
- ★★→「出題頻度がそこそこ高い合否を分ける問題」
- ★→「出題頻度が低い問題」
800問(肢)のうち★★★が92.6%(741問)。
出題頻度の高い問題がほとんどを占めており、当記事で紹介している一問一答問題集の中では最も初学者の基礎固めに向いてます。
2024年版の大きな改善点が2つあります。
それは、分冊タイプになったこと、そして付属アプリが12月から利用できるようになったことです。
本書は全部で397ページ。『トリセツ』の基本テキスト及び分野別過去問題集と同じ大きさ(A5版)です。
昨年版は1冊まるごと分冊なしの上A5判なので他社が出版している一問一答問題集より大きく重かったことが欠点でした。
その欠点を補うためか、2024年版は3分冊となり、携行性が良くなりました。
※アプリの利用方法とアクティベーション方法は本書を購入して確認してください。アプリの画像は『トリセツ』シリーズのレビューをご参照ください>>>『宅建士合格のトリセツ』シリーズ購入レビュー【宅建テキスト・問題集・一問一答】
第3段階学習におすすめ:出る順宅建士 ウォーク問過去問題集
◆第3段階学習に最もおすすめしているのは『出る順宅建士ウォーク問』1〜3です。

- ページ数:①権利関係342頁、〔2〕宅建業法364頁〔3〕法令上の制限・税・その他の分野410頁頁
- 分冊の有無:無
- 電子書籍の有無:有 Kindle版、楽天Kobo版→注:2024年1月9日時点ではAmazonではウォーク問③のKindle版が未掲載となっています。楽天Kobo版は3冊とも掲載されています。
- 分野毎の収録問題数:〔1〕権利関係169問、〔2〕宅建業法180問、〔3〕法令上の制限その他の分野201問
- テキストとの連携の有無:有 『出る順宅建士 合格テキスト』とリンク
本書は権利関係、宅建業法、法令上の制限その他の分野の合計3冊による4肢択一式分野別問題集となっています。
B6判と一般的な宅建テキスト・問題集のA5判より小さくコンパクトです。
3冊合計550問を収録。市販の宅建4肢択一式分野別問題集としては2番目に多い問題数です。
『出る順宅建士 ウォーク問過去問』は過去問習熟用の問題集です。基礎固めをしないまま本書を解くことは決しておすすめしません!
『ウォーク問』の特長は、収録問題集の多さのみならず、LECが長年蓄積している各問の正解率データ(合格者正解率と不合格者正解率)を各問に記載していることです。
宅建試験は合格者正解率66%以上の問題をきちんと得点できれば合格できます。基礎固めを終えた受験生は合格者正解率66%以上の問題の正解率を必ず100%にしましょう(無論、特A・A・Bの正解率も100%にしなければなりません)。
『ウォーク問』は、収録問題のレベルを次の4段階に分けています。これは第1〜3巻で共通しています。説明しておきます。
- 特Aランク:最も重要な問題
- Aランク:かなり重要な問題
- Bランク:まあまあ重要な問題
- Cランク:参考程度の問題
550問のうちSAランク問題の割合は72.9%です。
SAランク問題の割合は初学者の基礎固めに適しています。
しかしながら550問という収録問題数の多さは基礎固めには不向きです。
300問分野別問題集・一問一答問題集で基礎を固めた上で、本書で過去問を習熟する、という使い方をおすすめします。
本書に取り組むのであれば、少なくとも5月末までに基礎を固めておくことを強くおすすめします。
2024年版各巻の重要度ランク別収録問題数を記載した個別レビュー記事はこちらです>>>宅建ウォーク問過去問題集購入レビュー【宅建テキスト・問題集】
第2段階・第3段階学習用テキストと問題集を2冊に集約したい場合におすすめ:『宅建士 神テキスト』・『宅建士 神問題集』
◆『この1冊で合格!水野健の宅建士 神テキスト 2024年度版』のレビューは2024年版です。

- 条文番号:無
- テキスト部分のページ数:559頁
- 色使い:フルカラー
- 読みやすさ:読みやすいがフォントは小さめ
- 分冊の有無:無
- 電子書籍の有無:有 Kindle版と楽天Kobo版
- 問題集との連携:無(初版のため、誤植のリスクを回避)
- 内容について(国土法):○
『この1冊で合格!水野健の宅建士 神テキスト 2024年度版』はA5サイズ。分冊タイプが多くなった宅建テキストでは数少ない1冊丸ごと宅建テキストです。
「はじめに」「目次」「索引」を除くテキスト本体のページ数は559ページ。コンパクトに要点がまとめられている宅建テキストです。
電子書籍版もあります。こちらもそろえるとスマホ・タブレットがあればいつでも学習できます。
印刷はフルカラー。色使いをおさえているので『ユーキャンきほんの教科書』のような「どぎつさ」はありません。見やすくデザインされています。(『ユーキャン』は目がちかちかします)
テキスト本文と強調箇所や欄外注釈などのフォントを変えてむしろごちゃごちゃしたテキストが散見される中、すべて同じフォントで統一しています。
フォントは明朝体ではなくユニバーサルデザインフォント系。読みやすいです。
ただしフォントサイズは小さめ。読みにくいと感じる方(特に高齢受験生)もいると思いますが、情報を盛り込むため割り切ったのでしょうね。
各項目は優先度S(最優先)、A(重要)、B(普通)、C(後回し)のランク別。
まずはページ順に学習して完走し(できれば2月中に1周できると後が楽になります!)、2周目以降はランク別にSから集中的に学習すると良いでしょう。
テキストを開いてまず目に付くのは水野先生のイラスト付きの「会話」です。各項目の冒頭で、その項目での学習ポイントを会話形式で提示しています。
受験生にとってこの学習ポイント提示はこれから学習することの羅針盤となる必須情報。これがあるとないでは大違いです(どの市販テキストとは言いませんが、これがないと例えば国土法で事前届出・事後届出のどちらを重点的に学習すべきかを知らないままテキストを読み進めることとなります)。
学習を進めていくと、「冒頭の会話」を含めて水野先生のイラストが頻繁に登場します。これは補足事項・覚え方・注意点・学習法などが書かれている「重要ポイント」です。水野イラストの「重要ポイント」を意識しながら学習すると良いでしょう。
条文番号はありません(必須と言える農地法3条・4条・5条と宅建業法「34条の2書面」、「35条」、「37条」はちゃんとあります)。
内容(宅建業法の罰則と国土法)についてチェックしたところ、どちらも問題ありません。冒頭の会話および各重要ポイントにしたがって安心して学習を進めていけるテキストと判断しました。
各項目の重要ポイントはもちろんですが、豊富な図表が理解の助けとなります。
特に権利関係では4ページも使って権利関係の考え方を一通り提示しています。この図を読み込んでおくと権利関係の学習がスムーズに進みやすくなります。
本書は他の宅建テキストとは一線を画しています。それは一問一答を345問も収録していること。これが本書の大きなメリットとなっています。
次に紹介する『神問題集』は4肢択一問題332問を収録していますが、実は一問一答問題も992問収録しています。
本書と合わせると、一問一答問題だけで345+992=1337問。これは市販一問一答問題集で最も問題数が多い『史上最強の宅建士問題集』に次ぐ収録数です。
『神テキスト』・『神問題集』の2冊で学習する受験生は別途一問一答問題集を購入する必要はないでしょう。初学者にも、既学者・リベンジ組にもおすすめできる宅建テキストです。
『水野健の宅建士 神』シリーズには、分野別4肢択一の『水野健の宅建士 神問題集』があります。一問一答問題集と年度別問題集はありません(一問一答はテキスト・問題集双方に収録されているので不要です)。
なお、テキストとのリンクについてはX(旧ツイッター)にて、水野先生から直接「初版でページ数が不明で誤植が出る可能性が大きいので記載してない」(原文のまま)とのリプライをいただきました。このデメリットはあるものの、本書は丁寧かつコンパクトなテキストであり、『神問題集』と合わせた一問一答問題数が必要十分であるという2つのメリットがデメリットを補って余りあると判断しました。
では『神問題集』のレビューにうつります。
◆分野別4肢択一および一問一答問題集でもある『水野健の宅建士 神問題集』は2024年版の紹介です。

- ページ数:権利関係200頁、宅建業法224頁、法令上の制限・各種税等・免除科目248頁
- 分冊の有無:有 3分冊
- 電子書籍の有無:有
- 分野毎の収録問題数:権利関係99問、宅建業法111問、法令上の制限70問、各種税等・免除科目52問
- テキストとの連携の有無:無
『この1冊で合格!水野健の宅建士 神問題集 2024年度版』はA5サイズ。
LEC東京リーガルマインド講師・宅建水野塾主宰の水野先生による初の4肢択一形式分野別過去問題集です。過去問ベースとなっており、法改正対応等が必要な問題は改題されています。
収録しているのは1)権利関係、2)宅建業法、3)法令上の制限・各種税等・免除科目。各分野はそれぞれ分冊可。
見開きの左ページに問題、右ページに各肢の解答・解説が記載されています。
全体にフォントが小さめです。老眼の方はちょっとつらいかもしれません。
見やすさの感じ方には個人差がありますので、購入を検討する際はAmazonで書誌情報や誌面を確認したり、書店で手に取ってみてからにしましょう。
4肢択一問題を332問を収録しています。
332問の分野別内訳です。
- 権利関係→99問
- 宅建業法→111問
- 法令上の制限・各種税等・免除科目→122問
うち、法令上の制限70問、各種税等・免除科目52問
問題の重要度は★★★〜★の3段階に分けられています。
なお、本書は4肢択一問題の肢それぞれについても★が付いています。「はじめに」p.4に「★はとくに重要な選択肢です。しっかり理解しよう!」とあります。重要肢とそうじゃない肢とでメリハリを付けた学習を心がけましょう。
問題の重要度別の内訳は次の通りです。
- 権利関係→★★★60問、★★26問、★13問
- 宅建業法→★★★85問、★★20問、★6問
- 法令上の制限→★★★34問、★★32問、★4問
- 各種税等・免除科目→★★★28問、★★20問、★4問
332問の重要度構成は★★★207問、★★98問、★27問でした。※本書では「あえて」★問題を収録している場合があるとのことです(法令上の制限・各種税等・免除科目の問題080)。
本書は★★★問題が全体の62.3%。一方『トリセツ』はAランク問題が全体の89.3%。問題の重要度構成では『トリセツ』のほうが初学者向けと言えます。
ただし、本書の最大の特長は一問一答を含めた収録問題数の量の多さ、そして説明の丁寧さにあります。
本書は収録332問全問のページに一問一答を3問付加しています。
つまり、本書は4肢択一332問のみならず一問一答992肢をも収録している問題集でもあります。4択一問題と一問一答問題を合わせると、収録問題の肢数は2,321に上ります(個数問題・組み合わせ問題でアイウおよびアイウエオの過去問を複数収録しているため、肢数は単純に332×4ではないことを実際に購入して確認しています)。
300問4肢択一形式問題集の収録肢数は1,200。本書はその1.9倍の問題を収録していることとなります。
ちなみに当サイトでは3段階学習法を提唱しており、3段階目は『出る順宅建士 ウォーク問過去問1〜3』を推薦しています。『ウォーク問』3冊で計550問を収録しているので肢数は2200。
したがって、問題の量で言えば本書は「ウォーク問3冊分」を超えているのです。ただの300問クラス分野別過去問題集じゃないのです。
さらに言えば、『神テキスト』345肢を加えると2,666肢となります。問題演習は『神問題集』と『神テキスト』で十分です。
説明も丁寧です。
当サイト管理人が購入した300問クラス分野別問題集は5冊。うち、本書を含め4冊が2020年10月試験問10を収録しています。4冊全部掲載すると長くなるので『トリセツ』と『みんほし』における肢4の解説を引用します。
・「所有権は消滅時効にかかりません。」(『2024年版 宅建士合格のトリセツ 厳選分野別過去問題集』権利関係編p.21より)
・「所有権は消滅時効にかかりません。」(『2024年度版 みんなが欲しかった!宅建士の問題集 本試験論点別』p.251より)
一方、本書の説明は以下となっています(権利関係編p.23より)。
・「所有権が消滅時効にかかることはありません。時効取得により喪失することはあっても、自然に権利が消滅することはありません。」
顕著な例を挙げたかもしれませんが、本書は全般に説明が丁寧です。図や表も多用しています。
さらには単なる解説に留まらない「Ken's Point」という「練習問題に関連した解き方のコツや補足情報」(はじめに p.4より)を掲載。中には図表で紙面を占有されたためKen's Pointが掲載されていない問題もありものの、「水野先生の言葉」で各問題のポイントを伝えています。これは秀逸です。必ずチェックしておきましょう。
※2024年版『神テキスト』と2024年版『神問題集』はリンクしていません。テキストと問題集のリンク・連携を重視する方にとっては本書は選択肢から外れます。
また、収録問題の多さおよび問題の難易度構成からすれば本書は『トリセツ』よりも完走・周回しにくい問題集です。決して初学者向けとは言えません。
しかしながら、本書および『神テキスト』が収録する問題数からすれば、『神テキスト』・『神問題集』から『ウォーク問』に移行する必要はありません。
もちろん、一問一答問題集を別途購入する必要もありません。
『ウォーク問』に移行する必要がなく、一問一答問題集を購入する必要もないため、本書のみにメイン問題集を集約できるのはたいへん大きなメリットと言えます。
『ウォーク問』より収録問題数が少ない問題集への移行はあっても良いでしょう。当サイトで他の問題集についてデータを分析している最中です。分析を終え次第、追記します。
また、近年の宅建試験難化傾向に対応するのであれば、初学者であってもBランク問題は落とせません。Aランク問題を絶対に落とさないのは当然として、より多くのBランク問題に目配りしている問題集のほうが合格に近づきやすいかもしれません。
このため、初学者であっても本書及び『神テキスト』とのセット学習が視野に入ってきます。
※2024年4月17日追記 水野先生が本書の全問題解説演習ゼミ(解説動画)配信を開始しました!→6月24日現在、問1〜問95まで動画公開中です!!
水野先生ブログ(2024年4月1日)からの引用です→「一問一答は×の肢は一言解説で大丈夫でも〇の肢にはページの文字数の都合もあって解説が入ってません。答えは×だと思ったのに解答は〇になっているのは何故?という疑問を持つ方は多いはずです。
これから週一回定期的に毎回5問程度(30分くらい)ずつアップして参ります。
動画見ながら問題演習する際は解答する時間は特に設けないので一時停止して解答したら解説を聞くというやり方がよいかと思います。あと、わからない問題だけ確認できるようにチャプターもつけます。」
チャプター付きなので解きたい問題の解説のみの視聴もできます!
第1回は権利関係編問1〜5。まずはご覧ください!理解度がぐっと上がりますよ!!
権利関係問6〜10
権利関係問11〜15
権利関係問16〜20
権利関係問21〜25
動画解説は『トリセツ』に一日の長があったのですが、神問題集演習ゼミ配信によってを初学者であっても本書及び『神テキスト』とのセット学習が視野に入ってきます。
リベンジ組には特におすすめです。2023年版テキストおよび300問分野別問題集さらには一問一答問題集や『ウォーク問』もこなしてきた受験生には、本書と神テキストでリスタートしても良いと思います。
本書はインターネットサービスとして、正誤表、法改正情報、さらには令和2〜令和4年度宅建本試験過去問5回分の過去問解説PDFが付属しています(『宅建試験ドットコム』利用)。かならず参照しておきましょう。
本書の見開き左側問題文ページのタイトル下には3回分のチェック欄があります。3回と言わず何度も何度も、本書がぼろぼろになっても周回して「95%以上正解できるようになる」(「はじめに」p.2より)まで仕上げましょう。
『神』シリーズ2冊のレビューはこちらです>>>水野健の宅建士 神テキスト・神問題集購入レビュー【宅建テキスト・問題集】
5問免除対象の受験生および条文番号も含めて学習したい受験生向け:『出る順宅建士 合格テキスト』
◆5問免除対象の受験生および条文番号も含めて学習したい受験生には『出る順宅建士 合格テキスト』が良いでしょう。
※2024年版の紹介です。

- 条文番号の記載の有無:有(条文・判例も記載)
- 各巻のページ数:3冊合計1222ページ
- 色使い:二色刷り
- 読みやすさ:読みやすい
- 分冊の有無:無
- 電子書籍の有無:有 Kindle版と楽天Kobo版
- 問題集との連携:有 『出る順宅建士ウォーク問過去問』と連携
- 内容について:初学者向けとしては×だが上級者向けとしては○
最近の宅建テキストは分冊版が目立ちますが、LEC『2024年版 出る順宅建士 合格テキスト』は分冊なし、3冊シリーズとなっている宅建テキストです。
このテキストは次の3冊から成っています。
- 権利関係(430頁)
- 宅建業法(303頁)
- 法令上の制限・税・その他(473頁)
※ページ数はいずれもテキスト部分のみ(巻頭の「はしがき」、「本書の使い方」および巻末索引は含まず)。
総ページ数は1206ページにもなります。
ブログ管理人が知る限り、市販の宅建テキストでは最大の分量を誇ります。
本書は3冊とも条文番号のみならず、条文・判例まで記載しています。
初学者向けチェックポイントである国土法には24ページも割り当て、しかも事前届出制には6ページも費やしています。そこまでの情報は不要です。
国土法のみならず質・量ともボリュームが多すぎるため、宅建初学者にはまったくおすすめできません。ヘタしたら試験までに3冊とも完走できないかもしれません。ボリュームが多いので周回もままならない可能性も高いです。
ただし、宅建業・不動産業に従事している方で5問免除の宅建登録講習をLEC 東京リーガルマインドで受講する方は本書と同一内容の教材を使用するとのこと。
不動産業に従事されている方や、宅建既学者、条文についても学習したい宅建受験生、そして宅建はもちろんさらに上位の法律系資格を目指す上級者にはおすすめです。
もし初学者が本書を利用するとすれば、「600ページ程度の宅建テキストに載っていないこと」を調べるための「辞書」に限定して下さい。メインテキストに選んだらまず間違いなく消化不良を起こします。
本書の個別レビューは出る順宅建士 合格テキスト購入レビュー【宅建テキスト】です。
『とらの巻』、『直前予想模試』について
法改正情報入手用の『とらの巻』および直前予想模試についてはAmazon等で予約可になったら追記します→LECの直前予想模試を入手し、レビューしました。こちらをご参照ください。